
|
さらに、所得税の課税方法はその所得(あるいは収入)の種類により、「総合課税」「分離課税」「源泉分離課税」の3通りの課税方法に分類されます。(表19)
このように、厚生年金や国民年金などの公的年金の収入にも、雑所得として所得税とさらに住民税がかかってきますし、生命保険契約や積立年金などの私的年金についても掛金払込者本人が受け取るときには雑所得が、また、受給中に掛金払込者が死亡した場合に遺族がこれを受け取るときには相続税の課税対象となります。
ただし、公的年金についても障害年金や遺族年金は、年金の性格から非課税の級とされていますし、老齢(退職)に基因する年金などについても、年金という所得の性質を考慮してその税負担を軽くするため「公的年金等控除」という控除が設けられていて、その年金収入から公的年金等控除を差し引いて残った金額が(公的年金の)雑所得となります。
控除については後ほど詳しく述べることとしましょう。
所得税の課税システムは既に説明したように、個人が1年間に得た所得は10種類の所得のそれぞれに該当するかによって分類され、その所得に応じた計算方法でその所得金額を計算し、このうちサラリーマンなど源泉分離課税の適用を受けるものは、それを受け取った段階で天引きにより納税を済ませ、事業経営者などその以外のものは確定申告によって税金を精算することとなります。ただし、給与・退職所得だけはいささかの例外もあります。
申告された各種所得は、損益通算といわれる手続きを行った後、総合課税される総所得と(申告)分離課税される各所得に区分され、認められる所得控除を差し引いて総所得と(申告)分離課税される各所得の別にそれぞれ決められた税率をかけて所得税の合計を算出します。
表19 課税方法の種類とその内容
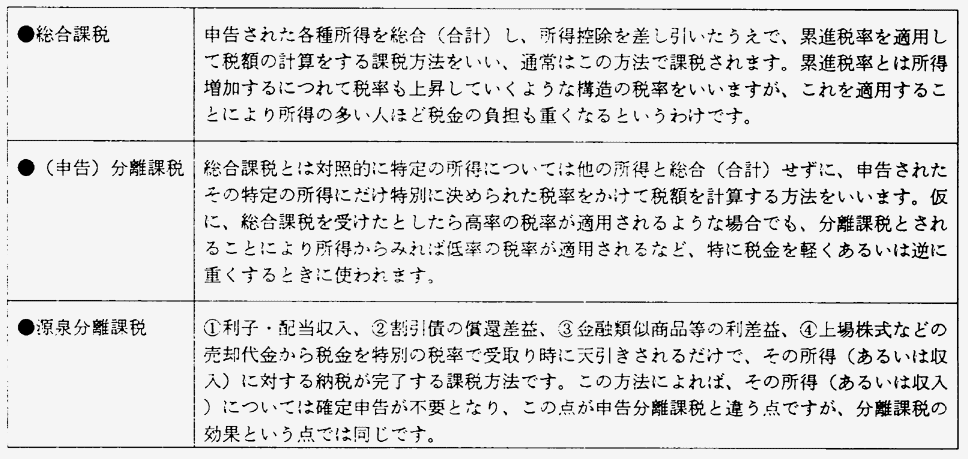
前ページ 目次へ 次ページ
|

|